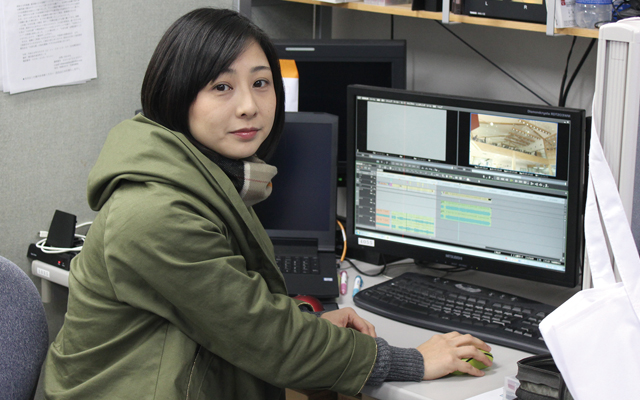一人でもいい。人の心を動かしたい。
自分が作った番組で誰かが感動してくれたら嬉しい。
ふだん見ているテレビの裏にはどんな人たちが関わっているのだろうか。ディレクターと呼ばれる人も画面には姿をみせない裏方の一人だ。タレントやカメラマンへ番組のコンセプトに沿った動きを指示するのが主な仕事というが、水谷さんに、これまでのキャリアと映像というクリエイティブな仕事への思いを伺った。
逆カルチャーショック
小学6年の終わり、水谷さんの生活は一変した。小学校の先生だった父が海外の日本語教師の公募に応じ、家族とともにインドネシアの首都ジャカルタに移住することになった。ただ親に言われるままの引越しだった。訳も分からず現地の日本人学校と使用人つきの自宅を行き来する毎日が始まった。当時のインドネシアは治安が悪く、外国人は使用人つきのセキュリティーの高い家に住むのが普通で、近所づきあいも、街に出歩くこともなく、現地の人たちとの交流はあくまで学校の管理のもと行われる恒例行事が主だった。「ただ、日本人学校の友達はみんな個性的で、制服はなく茶髪やミニスカートの子もいて、格好も好きなこともみんなバラバラでした。外交官や商社マンなどお金持ちの子どもが多かったせいか、周りの目を気にして行動するような子どもは少なかったですね。その分、お互い言いたいことも言い合えました」。日本人学校でありながら、周りと同じでなければ不安になったり、複雑な人間関係に悩んだりする日本的風潮は全くなかったという。思春期の真っただ中をそんな環境で過ごした。帰国して感じた逆カルチャーショック。そこには慣れない日本の高校生の文化、そして女子の文化があった。馴染めないまま、周りの女子と群れなかった水谷さんに残された選択肢。それは勉強だった。「がり勉で通しました。私にとって闇の時代です(笑)」。成績上位だった水谷さんは先生のすすめで国立大学の推薦入試を受けることになり、英語の論文試験対策に打ち込んだ。
マスメディアの世界に
大学時代は気持ちも外へと向かい、飲食業のバイトもやったし、塾の講師も経験した。一方で将来の仕事はとくにビジョンもなく、企業に就職して普通のOLになれればと思っていたが、入社試験には受からなかった。偶然親が目にした地元テレビ局の社員募集に応募した。そこがマスメディアの世界への入口となった。任されたのはレポーター。仕事をするようになってからそのおもしろさに惹かれていった。事件や災害の現場に出向き、テレビニュースの原稿を書くための取材を重ねた。報道記者というだけで『テレビの人間は来るな。あっちに行け』と不快感をあらわにする人もいた。当時話題となった阿久根市長と市議会の軋轢や米軍基地問題などにも密着取材していた水谷さん。仕事を覚え、仕事を任され、レポーターとしてのキャリアを積むはずでいた。しかし、出産をきっかけに4年半務めたテレビ局を離れることになる。
リスタート
子育てと家事に追われる日々が続いていたが、一方で仕事に対してやり残した感はぬぐえなかった。子どもを保育所に預け、社会復帰を決断。テレビ番組制作会社のディレクターとして採用された。ディレクターは、出演者や撮影スタッフに一つひとつのシーンをどう見せるかを指示するだけでなく、鹿児島など地方においては、企画、取材対象へのアポ取り、現場での取材、そして編集など一人でこなす部分も多い。なかでも重要な役割を尋ねると「やはり企画です。いま視聴者が何に関心をもっているのか、今の時代に何が感動を呼ぶのか、そんなことを考えながら、企画を立てるのが番組作りで最も難しい部分です。アイデアは、ネットをしていたりお茶をしていたり、いつどこから湧いてくるかわかりません」。その後、31歳で独立。責任は大きいが束縛のないフリーランスという形を選択した。テレビ番組の数分のコーナーから始まり、今ではドキュメンタリー枠の制作を依頼されるまでになった。これまでさまざまな番組のコーナーを手がけるなか、思い出に残るものを聞いたところ「絵でバトンをつなぐコーナーです。小学生たちが絵を描く姿を紹介していって、次回はまた別の小学校へとリレーしていくんです」。自身を振り返ると周りに流されながらたどり着いたのが今の仕事だというが、その眼差しに迷いはない。人に密着取材したもの、そして人の心を動かす番組を作りたいと語った水谷さん。そんな彼女の視点から生まれるドキュメンタリー番組が待ち遠しい。
取材:2016年12月